|
|
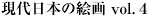 |
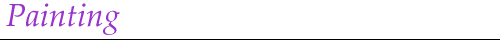
|
|

水門の在る風景 油彩 F100号 2003 |
口澤 弘 Kuchizawa Hiroshi
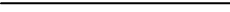
|
| |

|
|

黄色いかんざし 油彩 F4号 2008 |
外間正枝 Gema Masae
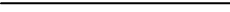
|
| |

|
|

新兵たちの休日 油彩 M80号 2007 |
小ヶ倉 明 Kogakura Akira
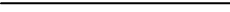
|
| |

|
|
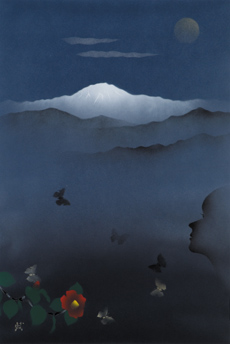
白山霊峰 静かな夜 油彩 P40号 2008 |
小練武志 Koneri Takeshi
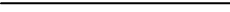
|
| |

|
|
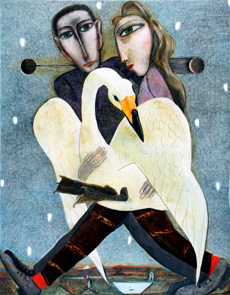
白鳥を連れて パネル・テンペラ・油彩 F50号 2007 |
小林裕児 Kobayashi Yuji
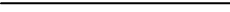
|
| |

|
|

私の風景 油彩 F130号 1981 |
紺野修司 Konno Shuji
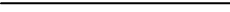
|
| |

|
|

これから 水彩・パステル 84.0×59.5cm 2006 |
斉木章代 Saiki Fumiyo
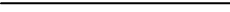
|
| |

|
|
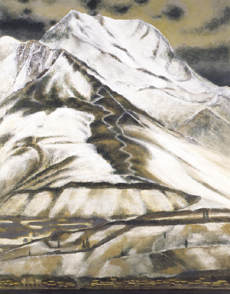
曠原 日本画 F50号 2006 |
齋藤 陽 Saito Akira
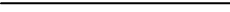
|
| |

|
|

残夢 油彩 F100号 2002 |
佐伯武彦 Saeki Takehiko
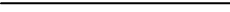
|
| |

|
|

Tomorrow 油彩 F100号 2005 |
酒井文子 Sakai Fumiko
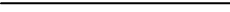
|
| |

|
| |
| PageTop |
|