|
|
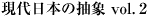 |
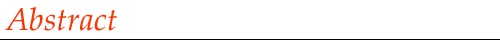 |
|

不死鳥は舞う 銅版 60×36cm 2007 |
深沢幸雄 Fukazawa Yukio
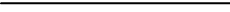
|
| |

|
|
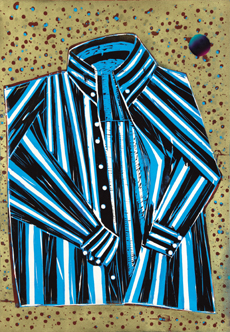
僕の青い縞のシャツ 木版画 90×60cm 2007 |
吹田文明 Fukita Fumiaki
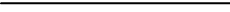
|
| |

|
|

ある光景 別珍 170×135cm 1993 |
藤川素子 Fujikawa Motoko
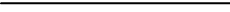
|
| |

|
|

ピンクのバラ 油彩・キャンバス F6号 2007 |
逸見 有 Henmi Tamotsu
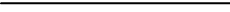
|
| |

|
|

moving…A アクリル F50号 2007 |
ヘンリー・マツダ Henry Matsuda
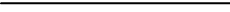
|
| |

|
|

始まりの形─ラセンと出会って'06 陶 300h×600w×400d cm 2005 |
星野 曉 Hoshino Satoru
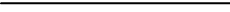
|
| |

|
|
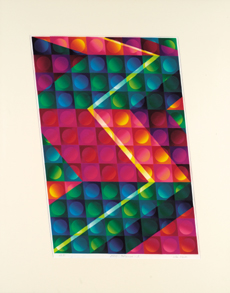
ZONE:Reflexion-A 木版画(鳥の子紙・水性絵の具) 71×47.5cm 2008 |
本田耕一 Honda Koichi
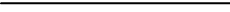
|
| |

|
|

重ねる 布・ネット・アクリル F60号 2002 |
前川 強 Maekawa Tsuyoshi
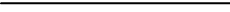
|
| |

|
|

アデンの媚薬 日本画・岩絵の具他 219×348cm
2008 第35回創画展 |
牧野一泉 Makino Kazumi
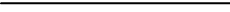
|
| |

|
|

音と光Ⅰ ミクストメディア+テクノロジー 60号 2008 |
真樹ゆうき Maki Yuuki
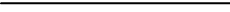
|
| |

|
| |
| PageTop |
|